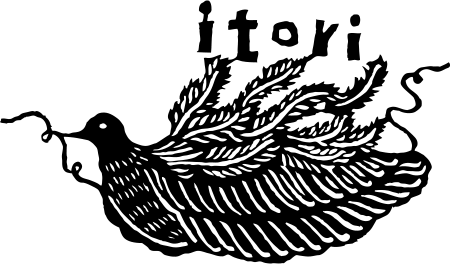Skog sjal / Forest shawl

ギャラリーcomoさんでの展示会、いとへんworksまであと4日となりました。
今回展示予定のストールです。森のストールと名付けました。
細かい柄ですが、木々や葉っぱや花の模様を織りました。
このストールを織りながら、スウェーデンに居た頃いろんな人と散歩した森の景色を思い出していました。
真っ暗で道がわからなくなりながらも、辿り着いた小屋のそばでたき火をしてみんなで暖をとりながら迎えを待った事も、真っ白な雪に覆われた森の中を歩いている時の、足音だけしか聞こえない感覚だったり、道無き道をただみんなの後を追ってついて行って見た知らない森の姿だったり、学校の裏山を登りきったところに広がる大好きな景色だったりと、いろいろな思い出があり、今思ってもとても人間と森(自然)の距離が近かったなあと思います。
いろんな森があって、それが織りで表現できることがとても楽しかったのですいすい織る事ができました。
アンゴラやカシミヤ、ウールの混合糸とラムウールの糸を使っています。
今まで使っていたお気に入りの糸が廃盤になってしまったので急遽新しい糸を注文しました。
新しい糸で織ったこのストールは、今までの糸よりもふんわりしています。このストールは色は地味目ですが、触り心地は最高です。
最近家の中もだいぶ冷えて来たのでたまにストールを巻きながら作業してたりしますが、このストールは軽くて暖かくて、巻いたままでも動きやすいのが気に入っています。
実物をどうぞ触りに来てください。他の色もありますので、また紹介すると思います。